“朝起きられない”月曜日から解放されるためのリアルガイド
「あぁ…また朝か。会社行きたくない…」
目覚ましの音と同時に、重たいため息がこぼれる。 昨日も精一杯頑張ったのに、なぜか今朝はとてつもなく重い。
カーテンの隙間から差し込む光が、出勤を促すサインのようで憂鬱。 布団から出るまでに要する意志の力が、日に日に大きくなっている気がする。
そして自己嫌悪の波がやってくる。
「まだ入社して1ヶ月も経ってないのに、こんなんじゃダメだ」 「みんな普通に頑張ってるのに、自分だけ…」 「甘えてるだけかも…」
もしあなたが今、このような朝を過ごしているなら、まずは深呼吸して、この記事をゆっくり読んでみてください。
あなたは決して一人じゃありません。そして、それは”甘え”でも”弱さ”でもないんです。
「会社に行きたくない朝」― それは4月の緊張がほどけたサインかもしれない
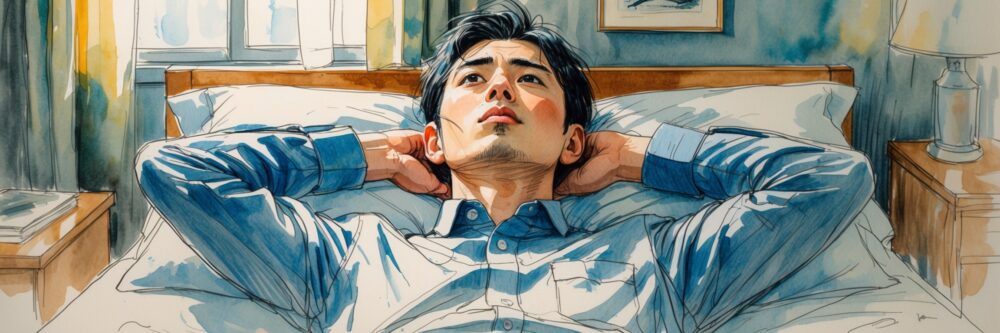
なぜ今になって「会社に行きたくない」が強くなるの?
4月、あなたはずっと走り続けてきました。
新しい環境、初めて会う人たち、覚えきれない業務用語、わからない仕事の進め方…。「失敗できない」という緊張感の中で、全力疾走の日々だったはずです。
名刺交換の作法を必死に思い出しながらの自己紹介。社内メールの書き方に四苦八苦。電話応対でのマナーに神経をすり減らす。先輩や上司の言葉を一言も漏らさないように集中する毎日。そして覚えきれない社内システムや手順を何度も確認する日々。
この「緊張モード」は、私たちの体が持つ自然な防衛反応です。新しい環境を乗り切るために、アドレナリンが出続け、脳と体は常に高い覚醒状態を維持していました。
そして、ゴールデンウィークの休みで、その緊張がふっと緩んだとき…
心と体はようやく本音を語り始めるのです。
「もう限界…」 「疲れた…」 「休みたい…」
これが、いわゆる”五月病”の正体なのです。
五月病とは何か? ― 医学的に理解する
五月病は医学的には「適応障害」の一種と考えられています。環境の変化によるストレスに対して、心身が適応しきれない状態を指します。
朝起きるのがつらい。会社に行く前から疲労感がある。やる気が出ない。集中力の低下。些細なことでイライラする。不安感や焦りが強まる。眠れない、または過眠。食欲の変化。頭痛、胃痛などの身体症状。
重要なのは、これらの症状が「甘え」や「意志が弱いから」ではなく、身体が発するれっきとした警告信号だということです。
五月病の本当の原因 ― 疲れを感じられるようになった証拠
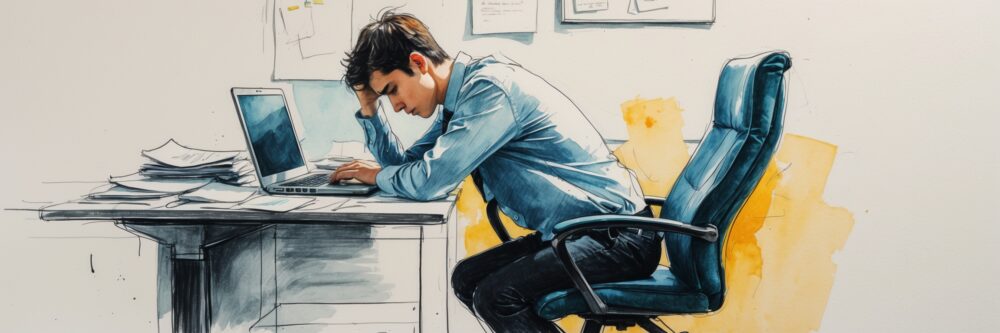
向き合う勇気があるからこそ現れる症状
実は、五月病に陥りやすいのは、真面目で責任感が強い人ほど多いと言われています。なぜでしょうか?
「新社会人として完璧にやらなければ」という強いプレッシャーをかけがち。小さなミスも「自分は役に立っていないのでは」と捉えてしまう。「迷惑をかけないように」と、自分の限界を超えて人間関係に合わせようとする。「新人が弱音を吐くなんて」と、つらさを表に出せず溜め込みがち。
これらは決して弱さではなく、むしろ「ちゃんと仕事と向き合おうとしている証拠」なのです。
感じなければ疲れることもない。逃げていれば五月病にもならない。あなたが症状を感じているのは、真摯に取り組んできた結果なのです。
こんな状況にも要注意!五月病の引き金になりがちな環境
五月病は個人の問題だけではなく、環境要因も大きく影響します。
単調すぎる作業や、逆に難しすぎる課題を与えられ続ける。頑張っても評価されているのかわからない状態が続く。職場の人間関係のルールがわかりにくく、常に気を遣う。通勤時間や残業で自分の時間が持てない。日々の業務が将来にどうつながるのかわからない。
「なんとなく朝がつらい」と感じる背景には、こうした複合的な要因が潜んでいることが多いのです。
「朝がしんどい」を軽くするスモールステップ10選

五月病を一気に解消することは難しいですが、少しずつ朝の気分を軽くするための小さな一歩を踏み出してみませんか?
全部やる必要はありません。あなたにとって「これならできそう」ということを、ひとつかふたつ見つけるだけで充分です。
【朝の目覚め編】
起きてすぐスマホを開く習慣、ついていませんか? SNSやメールを見ることで、脳は一気に“他人の情報”モードに入ってしまいます。 だからこそ、起きて最初の15分だけはスマホを見ず、自分だけの静かな朝を迎えるのがおすすめです。
「今日はまだ、誰ともつながらなくていい」そんな朝があってもいいんです。
もし余裕があるなら、10分だけ早起きしてみましょう。 慌ただしい朝より、少しでも自分にとって心地よい“余白”のある時間を持てたら、それだけで心の疲れは違ってきます。
そして、カーテンを開けて光を浴びる。窓際でお茶を飲んで、軽く伸びをしてみる。 「光の中で深呼吸する」——たったそれだけのことが、意外と効いたりします。
【心のケア編】
「今日も会社に行く自分、ほんとにえらい」 そんな言葉を、鏡の中の自分に向けて声に出して言ってみてください。 あるいは、心の中でそっとつぶやくだけでもいい。
誰かに言ってほしかった言葉を、自分がいちばん最初にかけてあげる。
それだけで、心の風向きが少し変わることもあります。
また、「今日は報告書を1ページだけ進めよう」とか「昼休みにコーヒーを飲みに行こう」といった、 ささやかな目標をひとつだけ決めておくと、一日に“芯”が生まれます。
そして、本当につらい日は、「体調不良」で休むことも選択肢にしてOK。 休むことを“後ろ向き”と捉える必要はありません。 「回復のためのステップ」として、勇気を持って選ぶ日があってもいいのです。
【モチベーション編】
「会社に行ったら、帰りにお気に入りのカフェでごほうびを」 そんな小さな“楽しみの予定”を立てておくと、朝の気分が少し変わってきます。
人は「嫌なこと」だけでは動けません。
“楽しみのある出勤”という形に変えてあげるだけで、出発の足取りが軽くなることもあります。
通勤中には、好きな音楽やポッドキャストを聴いてみてください。
会社に向かう“ただの移動時間”を、“自分のための時間”に変えてあげるだけで、世界の色が変わります。
【五感を活用する編】
柑橘系のアロマをたらしたり、お気に入りの音楽を流して朝を迎えたり。
音や香りといった五感を刺激することで、自律神経はやさしく整っていきます。
「いい匂い」「いい音」から、元気は静かに戻ってきます。
朝食にこだわってみるのもひとつの方法です。
毎日同じものでも、盛り付けを変えるだけで気分は変わります。 器をお気に入りのものにしてみたり、週に一度だけ“特別な朝ごはんの日”を作ってもいい。
「朝ごはんを楽しみに起きる」——そんな習慣を自分に許すことも、自分を大切にするひとつの形です。
「今日も行きたくない」と思う自分を責めないために

“あたりまえ”を見直してみよう
「社会人なら毎日元気に出社するのが当たり前」 「新人は常に前向きであるべき」 「弱音を吐くのは甘え」
こうした”あたりまえ”が、あなたを苦しめていませんか?
実は、多くの社会人が同じ悩みを抱えています。2023年の調査によれば、新入社員の約65%が入社後2〜3か月の間に「仕事へのモチベーション低下」を経験しているというデータもあります。
つまり、あなたは決して「ダメな新人」ではなく、適応過程で自然に現れる反応を経験しているだけなのです。
自分の感情を”観察”してみる
「行きたくない」と感じたとき、その感情を否定せず、まずは「なるほど、今そう感じているんだな」と受け止めてみましょう。
感情を抑え込もうとすればするほど、かえって大きくなることがあります。対話するように、自分の中の「行きたくない」という声に耳を傾けてみると、具体的な原因が見えてくることもあります。
「特定の業務が不安なのかな?」「あの人との関わりが緊張するのかな?」「単純に睡眠不足かも?」
原因がわかれば、具体的な対策も立てやすくなります。
この先、どうなっていくの? ― 五月病からの回復プロセス
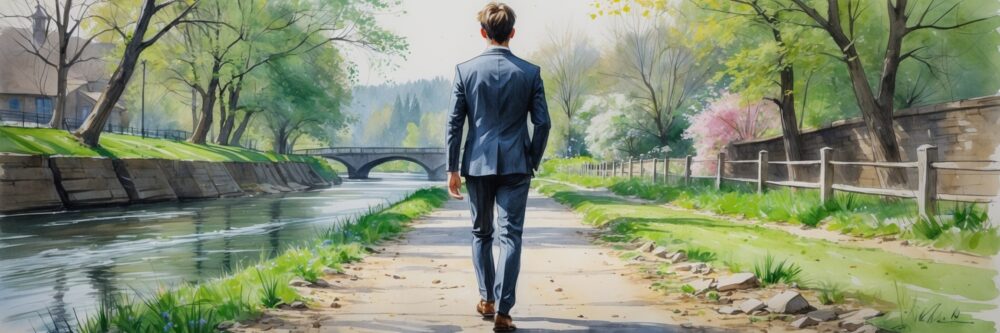
自然な回復のサイクルを知っておこう
五月病は永遠に続くものではありません。多くの場合、時間の経過とともに自然と症状は和らいでいきます。
1〜2週間目は症状のピーク期。3〜4週間目になると少しずつ慣れが生じてきます。1〜2ヶ月後には新しい環境への適応が進み、3ヶ月後には多くの場合、安定期に入ります。
ただし、これはあくまで目安です。無理に「〇月〇日までに元気になる!」と自分を追い込まないようにしましょう。
専門家の助けを借りるタイミング
朝起きられない状態が続く。食欲がなく、体重が急激に減少する。不安や焦りで夜眠れない。何をしても楽しいと感じられない。自己否定的な考えが強く、希望が持てない。
こうした状態が2週間以上続く場合は、一人で抱え込まず、専門家に相談することも検討してみてください。多くの企業では、メンタルヘルスケアの窓口や産業医への相談制度があります。また、外部の相談窓口(厚生労働省「こころの耳」など)も活用できます。
最後に ― あなたへのメッセージ

新社会人の皆さんへ。
朝、「会社に行きたくない」と感じることは、決して恥ずかしいことではありません。それは、あなたが真剣に仕事と向き合っているからこそ現れるサインなのです。
今は辛くても、少しずつ自分のペースを見つけていけば、必ず楽になる時が来ます。無理に「元気な自分」を演じる必要はありません。
「今日は少しだけ、昨日よりほんの少しだけ前に進もう」
そんな小さな一歩の積み重ねが、いつか振り返ったときに大きな成長になっているはずです。
「今、ここにいるだけでじゅうぶん」
そう思える朝が、また必ず戻ってきます。 それまでの間、どうかあなた自身を大切に、そして優しく労わってあげてください。
あなたは、ちゃんと頑張っています。
この記事があなたの心に少しでも余裕を作り出すきっかけになれば幸いです。コメント欄では、皆さんの五月病体験や乗り越え方も募集しています。一人じゃないことを、ぜひ感じてください。



コメント