──動かない私が、今の職場で見つけた静かな真実
「働かないおじさん」って、本当に悪者なの?
最近、「働かないおじさん」を再評価する記事がメディアの中で散見されるようになった。初めてそれらの記事を目にしたとき、私は眉をひそめた。「まぁ、それは極端な例外でしょう」と、半ば無意識に思っていた。だって、私たちは子供の頃から「一生懸命働くことが美徳だ」と教え込まれてきたのだから。
ところが、ある平凡な月曜日の朝、オフィスの窓から差し込む柔らかな光の中で自分自身を振り返ってみると、衝撃的な発見があった。「あれ、もしかして自分もその”動かない側”の人間なのでは?」という気づき。それは雷に打たれたような、しかし同時に奇妙に心地よい発見だった。
静かに存在するということ

私は、若手社員のように目の前の仕事に全力で飛びつくこともなければ、会議室で声高に自分の意見を主張することもない。多くの場合、私はただそこに座り、依頼された業務を確実にこなすだけだ。自分から積極的に手を挙げ、新しいプロジェクトにガツガツと食らいつくようなことはほとんどしない。
でも不思議なことに、そんな私が「職場で嫌われている」とか「煙たがられている」という感覚は―正直なところ、あまり感じない。もちろん、私の感覚が鈍いだけなのかもしれない。しかし、同僚や若手社員が私に対して明らかに距離を置いているような素振りは見受けられない。むしろ、何か相談事があるときには、しばしば私のデスクに足を運んでくる若手社員もいる。
彼らが私に相談してくる内容は実に様々だ。時には会社の方針への不満や、彼氏との関係の悩みといったプライベートな愚痴だったり。あるいはクレームを出したお客様へ謝罪に行く際の「同行してほしい」というお願いだったり。単純に仕事の進め方の確認だったりする。おそらく彼らは、私が「急かさない」「即座に評価しない」「じっくり聞く」という特性に、何かしらの安心感を感じているのかもしれない。彼らは私の「動かなさ」に何か価値を見出しているのだろうか?
「あの人、何もしてないじゃん」—昔の私の浅はかな判断

今から20年以上前、私がまだキャリアの入り口に立っていた20代の頃。あの頃の私にも、「あの人、いったい毎日何をしているんだろう?」と首を傾げたくなるような先輩がいた。会議では特に意見を述べることもなく、目立った業績を上げているわけでもない。オフィスの隅にある、いつも整理整頓された彼のデスクを横目に見ながら、「年を取るとああなってしまうのかな」と、どこか冷ややかな目で見ていたことを鮮明に覚えている。
「楽をしているな」「責任から逃げているな」―若かった私は、その先輩の内面を知ろうともせず、勝手に決めつけていた。そんな一方的な解釈が、どれほど浅はかだったかを、今の私は痛感している。あの時の先輩は、本当に何もしていなかったのだろうか? それとも、若かった私には見えない何かを担っていたのだろうか?
変わりゆく職場環境と「動かない人」の新たな価値

ここ数年、私の周りの職場環境は目まぐるしく変化した。技術の進化、働き方改革、そして予測不能なグローバル情勢。こうした変化の中で、若い世代が驚くほどの情熱と集中力で仕事に取り組んでいるのを日々目の当たりにしている。彼らの姿勢は称賛に値するものだ。
しかし同時に、彼らの疲労感も痛いほど伝わってくる。Slackやビジネスチャットでのやり取りを見ていると、常に時間に追われ、焦りを感じているような雰囲気が漂う。休憩時間にも仕事の話が続き、深夜まで通知音が鳴り続ける日も少なくない。
そんな状況の中で、「動かない人」の存在が、思いがけず職場に安定をもたらしているのではないだろうか。私がただそこに座っているだけで、誰かにとっての安心感になる―そんな都合の良い話を信じているわけではない。しかし、誰とも衝突せず、静かにそこに存在し続ける人の価値が、この忙しない時代だからこそ、見直されているように感じるのだ。
「動かないことで、見えることもある」―目に見えない貢献

動かないからこそ、見える景色もある。全体の流れを俯瞰できること。誰が疲れているか、どのプロセスに無駄があるか、どこにボトルネックが生じているか―こうした全体像は、一つの場所に留まり、冷静に観察することで初めて見えてくる。
例えば、先日あった新規プロジェクトの立ち上げ時のこと。若手たちが次々とアイデアを出し、熱気に包まれる会議で、私はいつものように静かに観察していた。そして気づいたのだ―誰も経理部門との調整について言及していないことに。過去の類似プロジェクトでは、その部分が最大のボトルネックとなったのを覚えていた私は、会議の終わりにそっと「予算申請の期限は来週ですが、経理との事前調整は済んでいますか?」と尋ねた。その一言で、チームは重大な障害を未然に回避できたのだ。
また、あるとき新入社員が顧客からのクレーム対応で青ざめた顔をしていた。彼女の上司は出張中で不在。私は単に「大変そうだね。何かあった?」と声をかけただけだが、彼女は「先輩、同行してもらえませんか」と頼んできた。実際に同席しただけで、彼女は自信を持って対応できたのだ。私がしたのは、ただそこに存在することだけだった。
自分があえて手を出さないことで、若手社員が新しいアイデアを試す余白が生まれることもある。彼らが失敗しても、すぐにフォローできる位置に控えているだけで、彼らの挑戦を支えることができる。
「働かない」は「価値がない」ではない―社会心理学の視点から

もちろん、これらの考えは単なる言い訳に聞こえるかもしれない。「要するに、自分が動かない理由を正当化しているだけじゃないか」と言われれば、一面では確かにそうかもしれない。
しかし、組織心理学の研究においても、同様の知見が示されている。チーム内に「行動志向」と「観察志向」の両方のメンバーがいることで、グループとしての意思決定の質が向上するという研究結果もある。また、心理的安全性を高める「安定的な存在」の重要性も指摘されている。つまり、「動かない人間」には、科学的にも裏付けられた組織的価値があるのだ。
私が以前勤めていた会社では、リストラの波が押し寄せた際、まず「目に見える成果を出していない人々」が次々と削減されていった。しかし、その後何が起こったか。組織の「記憶」や「暗黙知」が失われ、同じ失敗を繰り返すようになったのだ。「動かない人」の中には、組織の歴史や教訓を体現している存在もいるのだと、その時痛感した。
もし職場から「動かない人間」が一人残らずいなくなったら―毎日がスプリントのように全力疾走する環境になったら、組織はバランスを失い、長期的には息苦しさが増すのではないだろうか。
「働かない」の多様性を認める時代へ

「働かない」という言葉には、実はさまざまな種類がある。ただ怠けているだけの人もいるだろう。しかし、その中には「動かないけれど、じっくりと観察している人」「表面上は動いていないように見えるが、深く考えている人」も確かに存在する。
かつての日本では、とにかく「手を動かすこと」「汗をかくこと」が美徳とされた時代があった。しかし現代のような複雑で変化の激しい環境では、「焦らず、バランスを保ち、時に立ち止まって考える人」もまた、組織に必要な人材なのではないだろうか。
私は自分のことを、あえて「働かないおじさん(仮)」と呼んでみる。それでも、今の職場で一定の役割を果たし、必要とされているのなら、それはそれでいいのかもしれないと思っている。
おわりに:静止して見える風景がある
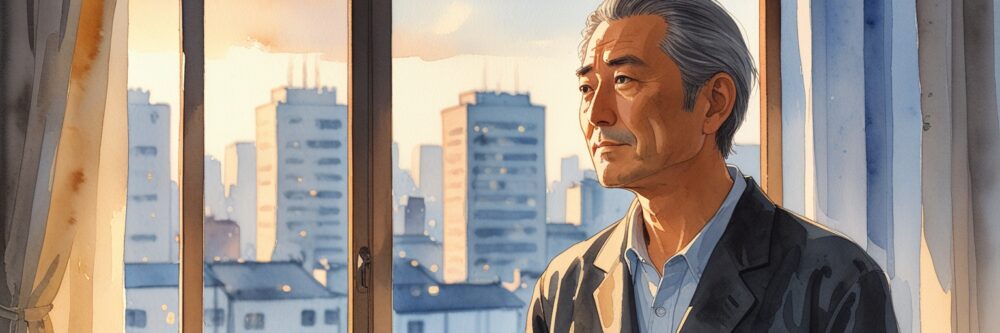
若い頃、目の前の仕事にがむしゃらに突き進んでいた時期には見えなかったものが、今は見える。それは、「動かない人間」もまた、職場の一部を、目に見えない形で支えているという事実だ。
ビジネスの世界では、走り続ける人がいる一方で、立ち止まり、全体を見渡す人も必要だ。その両方のバランスがあってこそ、チームは長期的に機能し続けることができる。
私は今日も、あまり目立たず、慌てず、でもしっかりとここに存在している。それが、今の私にできる最善の”働き方”なのだと思う。静止している私の目に映る風景が、誰かの役に立つことを静かに願いながら。


コメント